
冬の感染症の季節到来 早めの対策で乗り切ろう
- コラム
流行が早まっている今年のインフルエンザ。注射が苦手な子どもは点鼻ワクチンで予防を。

「風邪かも?」と思ったら、要注意。今年(2025年11月現在)はインフルエンザがすでにはやり始めています。この時期に気をつけたい感染症について、最新の特徴と対策を耳鼻咽喉科専門医の石井正則先生に伺いました。
今年のインフルエンザは流行の立ち上がりが早く、例年よりも1カ月早い9月下旬には流行期に入りました。すでに学級閉鎖も出ています。流行が早まった背景には、南半球で冬(日本では夏)に流行した型と同じウイルスが国内に持ち込まれ、その影響で流行の前倒しにつながったと考えられています。
インフルエンザには何種類かの型がありますが、例年1〜2月がピークとなるA型が現在流行しており、冬に向かってさらに感染が広がると見られています。B型はA型より流行時期が遅いことが多く、例年2月頃から流行し始め、春先がピークになります。なお、A型は高齢者がかかると重症化しやすいといわれていますが、B型でも重症化することは少なくありません。そのため、インフルエンザのワクチンは早めに受けることをおすすめします。
子どもには点鼻ワクチンが使える
令和7年度からは多くの自治体で、子ども向けの「点鼻ワクチン(生ワクチン)」が助成対象のワクチンに追加されています。2歳以上19歳未満が対象で、注射とほぼ同等の効果があるとされています。13歳未満の子どもは注射を2回受けるのが原則なので、注射の痛みもなく、鼻へのスプレー1回で済む手軽さは利点といえます。
ただし、接種後はウイルスが2週間ほど鼻に残るため、周囲に高齢者や持病のある人がいる場合は注意が必要です。また、微熱や鼻水などの軽い副反応が出ることもあります。

注射をいやがる子どもには点鼻ワクチンでインフルエンザ予防を。
新型コロナは激しいのどの痛みが特徴
一方、新型コロナウイルスも8月後半から9月にかけて再び増加しました。こちらも乾燥する冬にまた感染が拡大する恐れがあります。
最近の症状の特徴は、「激しいのどの痛み」「強い倦怠感」「高熱」の3つ。激しいのどの痛みで食事がとれない場合もありますが、入院治療は基本的に行われず、痛み止めを処方するなど対症療法を行います。ゼリー飲料などのどごしがよいものでカロリーをとって様子をみながら、回復を待ちます。
なお重症化する人は減りましたが、基礎疾患のある人や高齢者は依然として注意が必要です。重症化リスクのある人はワクチン接種を検討するとよいでしょう。

激しい咽頭痛には、刺激の強いものは避け、ゼリー飲料や冷やっこなど、のどごしのよいものを。
咳が長引く感染症にも注意を
インフルエンザや新型コロナ以外にも、咳が長引く感染症が増えています。とくに、急に寒くなってきた10月下旬からはマイコプラズマ肺炎が増加傾向にあります。
マイコプラズマ肺炎、百日咳、RSウイルス感染症などは、いずれも発熱や倦怠感が少なくても咳が続くのが特徴です。2週間以上咳が止まらない場合は、耳鼻咽喉科よりも呼吸器内科を受診するのがよいでしょう。胸部レントゲンや抗原検査、PCR検査、血液検査などで診断がつきます。
今季は、複数の感染症が同時に流行し、複数感染する可能性もあります。日頃から手洗い、マスク着用、うがいを心がけましょう。早めのワクチン接種と症状に応じて適切に受診することが、重症化を防ぐ大切なポイントです。
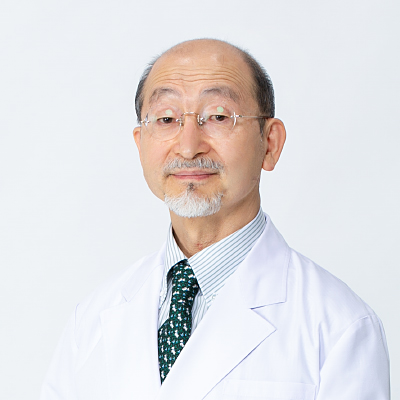
石井正則(いしい まさのり)先生
JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長
日本耳鼻咽喉科専門医。神経耳科(めまい、耳鳴り、難聴)や自律神経の診察や検査も得意としている。ヨガの公認インストラクターでもあり、院内ヨガやストレス疾患の専門治療施設で指導。耳鼻咽喉科心身医学研究会の発起人メンバーであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙医学審査会委員もつとめる。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など幅広く活躍。
制作協力:NHKエデュケーショナル








