
耳鼻科医から見たアーティストと演奏 第31回
- コラム
耳鼻科医の立場から、医学と演奏を探る
意外なことに、これまでこの連載では、ゲストにサクソフォーン奏者を呼んだことがなかった。そこで、話題の女性サクソフォーン奏者、住谷美帆さんにお声がけした。この楽器の奏者も楽器特有の悩みを持っていた。
<音楽之友社刊「音楽の友」2025年9月号掲載>

近年、目覚ましい活躍を続けている住谷さん。サクソフォーン奏者は竹田先生が希望して実現した
喉、首の脱力
私の生徒たちは、喉周辺の首に力が入ってしまうという悩みを持っているかたが多いですね。
首の力だけを抜こうとしても、なかなか抜けません。身体はつながっていますので、ほかの身体の部位も緩めます。自分が研究している、アーテム・トーヌス・トン(Atem-Tonus-Ton)という呼吸法があります。ドイツ語で、アーテム=呼吸、トーヌス=医学的には筋肉の張力、トン=声・音。呼吸と音をつなげる筋肉の使いかたについてのエクササイズです。そのエクササイズでは息を吸うとき、背中ひいては仙骨をふくめた骨盤のほうまで緩めてあげると、首の力も緩みやすいと教えます。もう一つは、サクソフォーンをくわえると支えがかかり、首にも楽器の荷重がかかってしまいます。顎関節を痛める人もいます。顎関節症になると、口を開けにくくなり、ますます演奏に負担がかかります。それだけではありません。口の開閉に関わる外喉頭筋群という筋肉群があります。首の喉頭の上には舌骨があり、喉頭とつながっています。舌骨上筋群と舌骨下筋群が外喉頭筋群にふくまれます。それらで口を開閉しています。楽器をくわえて演奏するときは、そのあたりの筋肉も働くわけです。さらに外喉頭筋群は喉頭を上下させたり、声帯の運動にもかかわったりします。このことで音色も変わります。これらの筋肉が使われると首にも力がかかり、固くなりやすくなることも考えられます。それとサクソフォーンはストラップで首から吊り下げていますが、たとえば、ストラップの使いかたなどで負担を軽減できないかと。楽器を支える腕や指にも負担はかかると思うのです。ストラップにはたくさん種類がありますよね。
そうなのです。ストラップによって音もかなり違いますし、いまは昔に比べてたくさんのタイプがあります。負担がかならないようなものを選ぶことが大切だと思います。
首に引っ掛けるタイプですと、首で支えようとするので、また首に力が入ってしまいます。だから、ショルダーのタイプのほうがよいかなと思います。でも、胸の広がりとは逆方向に負担がかかります。自由に胸を広げることができる方が、息を取りやすいのです。
マッサージと筋トレ
普段から、マッサージなどで、もみほぐしたほうがよいかな、と思っています。実際に効果はあるのでしょうか。
それはよいと思います。流行っているのは、筋肉を覆っている膜(筋膜)を軽くほぐす方法です。筋肉の膜は全身つながっていますので、そこだけではなく、だんだん広げてやってみてください。
楽器を持って移動する際、肩が凝ってしまうときもあります。ひどくなると、息が入りにくくなるような感じがします。
スポーツ選手は、試合の前にストレッチをいろいろ行っています。でも、演奏前にストレッチをする音楽家は少ないと思います。本当はやったほうがよいのです。スポーツ医学より、音楽・芸能系の医学は遅れていると言われています。
じつは、1月からパーソナルジムに行っています。私のまわりで筋肉トレーニングを行っている管楽器奏者はほとんどいません。むしろ、筋肉がついたら吹きにくいと言う人もいます。私のトレーナーは、運動前にストレッチを取り入れています。それを、楽器を吹く前に取り入れてみたところ、息をかなり取り込めるようになりました。それから、筋トレをやっていると、腰や肩の痛みがなくなったり、軽減されたりしました。積極的にストレッチをやったほうがよいと実感しています。
「鼻抜け」をシンクロのスイミング用の鼻栓をつけて克服しました(住谷)
休んで回復させたほうが鼻抜けしにくいと思います(竹田)
鼻抜き
気になっているのは、鼻抜けです。長時間が吹いていたり、疲れていたり、息のスピードが速い曲を吹いていると、いきなり息が鼻から抜けてしまって、吹けなくなってしまいます。私は、シンクロのスイミング用の鼻栓をつけて練習するなど、自己流で克服しました。正しい直しかたはあるのでしょうか。
それが難しいのですよ。息の流れには口のほうに行く道と鼻のほうに行く道があります。口の奥のほうで口と鼻の間を遮断しているのが、軟口蓋です。それが上がると、鼻のほうには行きません。管楽器奏者は鼻抜けしないように、そこを上げたまま演奏しています。「あー」と母音を出すとき、口蓋垂はたいてい上がっています。それを動かしている筋肉が疲れると、上げっぱなしにできなくなり遮断できず鼻抜けが生じます。たとえば、口の中に圧がかかると、それを遮断しなければいけません。リードを調節するなどして、塞ぐ力を多少軽減できる可能性はあります。長時間練習する人は、鼻抜けしやすいですね。筋肉をずっと使い続けると、筋肉に疲労物質が溜まってしまいます。ですから、休憩を挟んで回復させたほうが鼻抜けしにくいと思います。それから、ものすごく頬を膨らませる吹きかたは、口腔内の圧が高まり、軟口蓋に負担がかかりやすいと思われます。
できる限り頬を膨らませない奏法がよいですよね。

紙を使って説明する竹田先生(左)
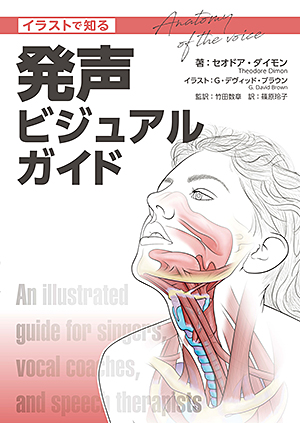
イラストで知る発声ビジュアルガイド
セオドア・ダイモン 著
竹田数章 監訳
篠原玲子 訳
【定価】2750円(本体2500円)
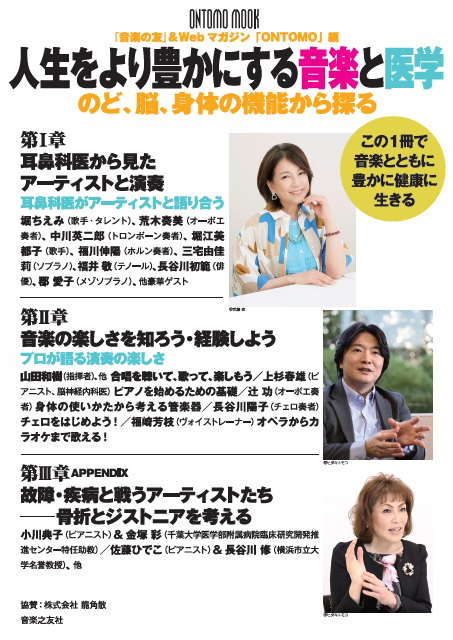
ONTOMO MOOK『人生をより豊かにする音楽と医学』-
のど、脳、身体の機能から探る
竹田数章/道下京子/堀ちえみ/堀江美都子/三宅由佳莉/山田和樹/上杉春雄/小川典子/他
【定価】1,650円(本体1,500円+税)音楽之友社刊
https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?id=963760
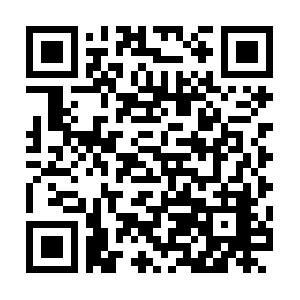
プロフィール

住谷美帆 (すみや みほ)
1995年生まれ、茨城県出身。12歳でサクソフォーンを始める。高校時代から数多くのコンクールで優勝および入賞。東京藝術大学を首席で卒業、アカンサス音楽賞、安宅賞及び三菱地所賞を受賞。第6回秋吉台音楽コンクール第1位、総合グランプリ(山口県知事賞)受賞。第34回日本管打楽器コンクール第2位。2018年7月、スロヴェニアにて開催された第9回国際サクソフォンコンクールで女性初の優勝。2022年アイオロス国際管楽器コンクール サクソフォン部門第2位、総合第5位受賞。TV朝日、日本テレビ、NHK-FM等、メディア出演も多い。これまで数多くのオーケストラ等と共演。令和2年度茨城県知事奨励賞受賞。
■公演情報
◎住谷美帆サクソフォンコンサート
〈日時・会場〉10月25日14時・清瀬けやきホール 大ホール〈共演〉山田武彦(p、お話)〈曲目〉デズモンド《テイク・ファイヴ》、ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》、シュルホフ《ホットソナタ》、他〈問合せ〉チケットプレイガイド カンフェティ 050-3092-0051

竹田数章(たけだ かずあき)
1959年生まれ、京都府出身。仙川耳鼻咽喉科院長。日本医科大学大学院博士課程卒業。医学博士。現在仙川耳鼻咽喉科院長。桐朋学園・洗足学園非常勤講師。音声生理学や臨床音声学の講義を行う。文化庁能楽養成会(森田流笛方)研修終了。趣味は音楽、スポーツ、観劇、フルート、書道。監訳書に『ヴォイス・ケア・ブック 声を使うすべての人のために』(ガーフィールド・デイヴィス&アンソニー・ヤーン著、音楽之友社刊)、『発声ビジュアルガイド』(セオドア・ダイモン著、音楽之友社刊)。ONTOMO MOOK『人生をより豊かにする音楽と医学-のど、脳、身体の機能から探る』(音楽之友社刊)









