
温度変化で鼻水やくしゃみ? 寒暖差アレルギーとは
- コラム
風邪とも花粉症とも違う、寒暖差アレルギーの症状と対策

急激な温度変化で鼻やのど、気管支も敏感になり、鼻水や鼻づまり、くしゃみ、頭痛、口呼吸によるのどの痛みや乾燥感、咳込みなどの症状が出るものを「寒暖差アレルギー」といい、温度差が7度以上になる場合に発症しやすいといわれています。
お風呂から上がって寒い場所へ移動したり、寒い中で熱い食べ物を食べたりしても症状が出ることもあります。
アレルギーという名称がついていますが、花粉やハウスダストなどアレルゲンから引き起こされるわけではないため、正確にはアレルギーではありません。
医学的には、「血管運動性鼻炎」といい、急激な温度変化によって自律神経が乱れ、それによって症状が現れると考えられています。
もし、発熱や目のかゆみ、充血といった症状がなければ、寒暖差アレルギーかもしれません。

外出や帰宅時など急な温度変化で、花粉症と似たような症状が起こる
加齢とともに症状が現れやすいが、最近は若い人にも増えている
寒暖差アレルギーは、一般的に加齢とともに増加することがわかっています。ところが、最近では加齢と関係なく、若い世代でも症状が出る傾向があります。その理由のひとつが、酷暑による身体への影響です。秋になっても暑い日が続き、身体がエアコンの環境に慣れてしまうため、温度調整が適切に働かなくなってしまい、症状が出やすくなっていると考えられます。
さらに、地球温暖化などにより、日本の四季の変化にも影響が出ています。夏から秋だけでなく、秋から冬、冬から春、春から夏でも同じように、寒暖差が激しい環境になりつつあるため、しっかり対策をとることが大切です。
寒暖差アレルギーの対策
寒暖差アレルギーは、激しい気温差による自律神経の乱れが原因になるため、天気予報であらかじめ気温差が大きいとわかれば、外出時には、ストールなどで首を温めたり、カーディガンやコートなど羽織るものを用意したりするなど、温度調整を心がけましょう。また、マスクをつけると鼻腔を通る冷気をさえぎることができます。
皮膚を温め、血流をよくすることも予防にとても効果があります。とくに、足湯で寒暖差アレルギーの症状が抑えられたという研究報告があります。ストッキングや生足をやめて厚手の靴下を履いたり、カイロで足裏や下半身を温めたり、軽い運動をしたりするのも、血行をよくするのにおすすめです。
また、自律神経は、ストレスや不規則な生活、睡眠不足でも乱れやすいので、バランスのよい食事と十分な睡眠をとるようにするなど、生活習慣を見直すことも大切です。

大きめの洗面器やバケツなどに湯を張り、足首まで浸かる「足浴」で血行を促進
治療は対処療法が基本
衣服などで温度調整を心がけたり、下半身を温める対策をとったりしても症状が出る場合、原因が細菌やウイルス感染、アレルギー性鼻炎などではないため、治療としては症状をやわらげる対処療法が中心となります。症状が軽い場合は市販の点鼻薬で抑えることもできますが、症状がひどい場合や、症状が長引く場合は、耳鼻咽喉科を受診しましょう。別の病気が隠れているかもしれないからです。
寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)の治療は、基本的には粘液を柔らかくして炎症を抑える薬(消炎酵素剤)、また抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬が症状を緩和することがあり、これらは医師の処方による治療になります。
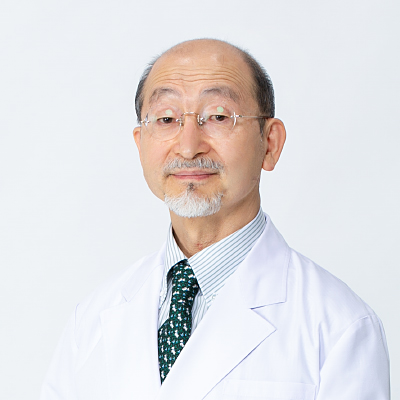
石井正則(いしい まさのり)先生
JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科診療部長
日本耳鼻咽喉科専門医。神経耳科(めまい、耳鳴り、難聴)や自律神経の診察や検査も得意としている。ヨガの公認インストラクターでもありストレス疾患の専門治療施設やヨガスタジオで指導。耳鼻咽喉科心身医学研究会の発起人メンバーであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙医学審査会委員もつとめる。 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など幅広く活躍。
制作協力:NHKエデュケーショナル









