
いつから始まる? 子どもの「声変わり」
- コラム
声変わり時期の向き合い方とケア、変声障害とは?

子どもの声変わり、これって普通? いつまで続く? 早すぎたり、遅すぎたりする場合は病気が隠れている場合もあるという思春期の訪れ。個人差の大きい声変わりについて、高橋幸子先生にお話を聞きました。
お子さんが思春期に入って大人へと成長するとき、生殖に適したからだのつくりに変化していきます。これを「第二次性徴」といい、男児は13歳前後、女児は11歳前後から始まります。
声変わりは第二次性徴のひとつで、男女ともに起こりますが、とくに男児はのどぼとけが急に大きくなり、外見的にも目立つようになります。また、男児は声帯も長くのび、厚くなります。このとき、発声を調整する筋肉の発育が、声帯の発育に追いつかず、「高い声が出ない」「声が裏返る」「声がかすれる」といった症状が出やすくなります。
なかには声が出なくなる、痰がからむというケースもあり、程度には個人差があります。
こうした症状の出る時期を「変声期」といい、通常3カ月から1年ほどで成人の声に落ち着いてきます。変声期を経て、男児は声域が1オクターブほど低く、女児は低音域が3度ほど低くなります。
女児の場合は、第二次性徴での声帯の変化はわずかで、声の変化もさほどなく、本人や家族も気がつかないことが多いようです。
声が落ち着くまで長くかかるケースも
変声期は発声が安定せず、高い声が出づらくなるので、音楽の授業などでうまく歌えなかったりして、お子さん自身、変化に驚いたり、ストレスを感じたりすることもあるでしょう。この時期は、無理に高い声を出す練習などは控えます。
また、この変化は病気ではなく、大人になるための変化であるとお子さんにしっかり伝えることも大切です。
変声期が終わっても、裏声や高い声をうまく出せるようになるまで時間がかかるケースもありますが、2年間くらいで安定することがほとんどです。
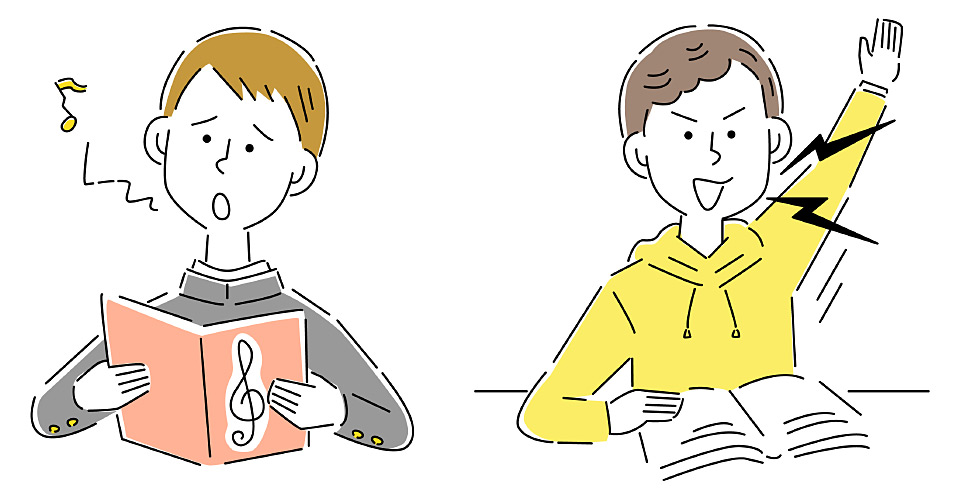
声変わり中は、無理して歌わない、大きな声を出さない。
まれにある「変声障害」
声変わりの経過において、喉頭の変化に声の出し方をうまく合わせられず、声が高いままとなってしまう状態を「変声障害(声変わり障害とも)」といいます。主な症状は、「低い声が出せない」「声がひっくり返る」などが挙げられます。治療には、低い声を出す発声練習を行います。
変声期が2年以上続く場合は、こうした治療が必要になることもありますので、耳鼻咽喉科を受診するようにしましょう。
声変わりが早すぎる「思春期早発症」、声変わりがこない「思春期遅発症」
男児の声変わりが10歳ごろから始まり、ひげも生え始めるなど、第二次性徴が現れるのが、通常よりも2〜3年早い場合、「思春期早発症」が疑われます。低年齢で急速に体が成熟するため、はじめはほかの子どもより身長が高いのですが、結果的に小柄のままで身長が止まってしまったり、まれに病気が隠れていたりすることがあります。
逆に、男児で14歳以上になっても声変わりがこない場合、「思春期遅発症」と考えられます。多くは体質性のもので、たんに標準より遅く、第二次性徴が出現するケースがほとんどですが、性ホルモンが出ない性腺機能低下症でないかの見極めも重要です。
いずれも、15歳未満であれば、まずは小児科で受診します。15歳以上の場合は内分泌代謝科などの専門医の診察を受けましょう。

教えてもらった先生:高橋幸子先生
産婦人科医。埼玉医科大学医療人育成支援センター・地域医学推進センター助教。埼玉医科大学医学教育センター、埼玉医科大学病院産婦人科助教を兼担。
全国の小学校・中学校で性教育の講演を数多く行う。著書に『12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育』(日本文芸社)、共著に『小学生おまもり手帳』などがある。
制作協力:NHKエデュケーショナル









