飲み込めない
飲み込みづらくなる原因は?
食べたり、飲んだりした物は、口から咽頭を通って食道へと送りこまれます。しかし、その一連の流れのどこかに障害が起こると、うまく飲み込むことができません。障害が起こる要因として、口では顔面麻痺や舌下神経など神経の障害、咽頭では炎症や咽頭がん、脳血管障害によるもの、食道は膠原病(こうげんびょう)などの全身性の病気や食道がんなどが挙げられます。
どの部分に障害が起こっているかは、色のついた水を飲み込む様子を観察したり、造影剤を使ったり、様々な検査で調べます。
固形物が飲み込みにくい場合は、口や咽頭、食道そのものに異常が起きていることが多く、液体を飲み込みにくい場合は神経や筋肉が原因となっている可能性が高いです。
飲み込みづらさが続くと全身に影響することも
飲み込みづらさが続くと水分量や食事量が減ってしまい、脱水になって意識障害やけいれんを起こしたり、栄養不足になったりすることがあります。また、食べる楽しみを失って、気持ちの面で落ち込んでしまうこともあります。
高齢になると飲み込みにくさを感じることが多いため、高齢者の家族は「食事中に疲れている」「食事に時間がかかるようになった」「体重減少がある」などの変化に気づいた場合は、飲み込みづらさがないか本人に確認するとよいでしょう。
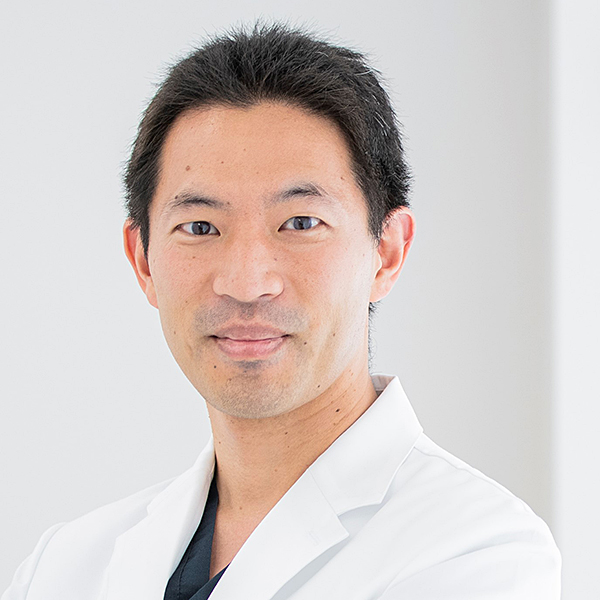
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定専門医
- 耳鼻咽喉科専門医研修指導医
- 日本頭頸部外科学会認定頭頸部がん専門医
- 日本気管食道科学会認定気管食道科専門医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定喉頭形成手術実施医
- 日本音声言語医学会認定音声言語認定医
- 痙攣性発声障害ボトックス施行医
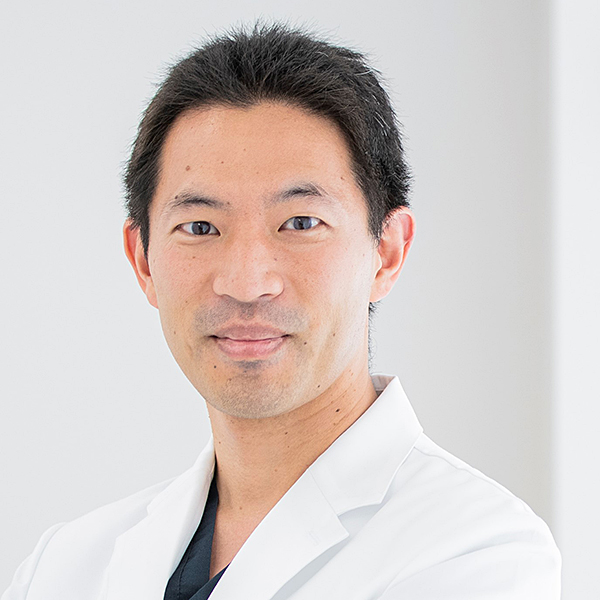
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定専門医
- 耳鼻咽喉科専門医研修指導医
- 日本頭頸部外科学会認定頭頸部がん専門医
- 日本気管食道科学会認定気管食道科専門医
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定喉頭形成手術実施医
- 日本音声言語医学会認定音声言語認定医
- 痙攣性発声障害ボトックス施行医



