
耳鼻科医から見たアーティストと演奏 第24回
- コラム
耳鼻科医の立場から、医学と演奏を探る
連載4年目、24回目にして、初めてのファゴット(バスーン)奏者が登場。長哲也は2018年に大学卒業と同時に東京都交響楽団の首席ファゴット奏者に就任した俊英だ。さて、ファゴット奏者特有の悩みとは……。
<音楽之友社刊「音楽の友」2024年7月号掲載>

長(左)の兄がラグビーをしていたとのことで、飾ってあったラグビーボールをきっかけに、中高時代ラグビー部だった竹田先生(右)と、ラグビーの話で盛り上がった
タンギング、そして呼吸と姿勢
タンギングについてです。とくに私は舌の動きが速くなく、どこか苦手意識があります。舌の長さや口のなかの作りも関係あるのでしょうか。
舌の長さに関しては、舌小帯短縮症といって、ベロの下にある小さなエラが短かすぎ、舌が前に出ない人がいます。治療したほうがよいケースもあります。舌小帯を切る手術になります。
発語などに影響があるのでしょうか。
多少あります。
シングル・タンギングが遅いので、早いうちからダブル・タンギングを鍛えて補っています。トレーニングなどによって、シングル・タンギングは早くできるようになりますか。
シングルのTTTTとダブルのTKTKが同じスピードでできるかどうかの問題です。やりきれるならば、問題はないと思います。舌がこわばってしまう人がいます。速いスピードのタンギングで緊張してしまい、動きが悪くなります。そういう時は、舌をふくめてリラックスさせ、タンギングの練習を続けていくとよいと思います。なかなか舌の緊張を抜くのは難しいですね。RRRと巻き舌を発音して力を抜くトレーニングもあります。僕のやっているアーテム・トーヌス・トン(Atem-Tonus-Ton、呼吸―身体の使い方―声、音)というドイツの呼吸法ですが、その先生がおっしゃるには、骨盤など後ろのほう…… たとえば仙骨(尾てい骨と腰骨の間にある骨)のあたりを緩めてやるとよいと。息を吐いたあと、仙骨あたりをふくめ、身体が自然に緩まったときに、息が自然に流れ込んできます。これをアーテムリフレックス(Atem Reflex 呼吸の反射)と呼んでいます。これをやることで、喉のまわりが緩みやすくなります。
仙骨を意識したことはありませんでした。
背骨の終着点的なところです。背骨には脊髄神経が走っています。腕を動かしたり足を動かしたりする神経です。呼吸もそうです。座骨神経痛と呼ばれている痛みが走ったりする人も、腰のあたりを傷めていますね。姿勢の問題もあります。
最近は大丈夫ですが、腰が痛い時期がありました。ファゴットは右側に構えますので、左側で支えることになります。
楽器は、どうしても不自然な姿勢になりがちです。極端に身体に負担がかかるような姿勢は修正したり、演奏後にクールダウンしたりしたほうがよいと思います。
★エクササイズ
腰を痛めやすい人で、反り腰のようになっていることがあります。反り腰は、腰の筋肉のバラ ンスが崩れることで生じます。腰を反らす筋肉が過剰に働いていたり、逆にお腹の筋肉が弱く なることでも反り腰になります。
★エクササイズとしての一例
椅子に浅めに座り、腰を反らさず上半身をまっすぐに引き上げるような姿勢をとります。頭も自然な位置をとります。手を太ももの上に載せ、息を吸いながら片足ずつ3〜5㎝、ゆっくり5つ数えるぐらいの時間持ち上げます。そうしたら息を吐きながら足を下してゆるめます。これを5回ずつ行います。
聴覚保護のための耳栓をすることがあります (長)
大きな音を聞き続けていると、耳に障害が出る可能性があります(竹田)


ファゴットの構造を説明する長(左)
耳栓
最近、聴覚保護のための耳栓をすることがあります。所属オーケストラが、どの音域も均一に抑えてくれる耳栓を作ってくれました。
ご自分の型を取って作ったのですか。
色が赤と青とで違うのは、右左を示す印ですか。


そうです。フィルターで、下げられるデシベルを変えることもできます。本番のときにも着けています。お聞きしたいのは、木管楽器奏者の真後ろで演奏される金管楽器の音によるリスク。それから、人によっては耳栓を作ったものの、なかで共鳴してしまい、聴こえるけれども音が取りにくい…… その難しさをうかがいたいです。
大きな音を聞くと耳がやられます。音響外傷と言います。85デシベルという音の大きさ。それ以上の音を聴くのは危険です。85デシベルは、うるさい電車内や交差点で人との会話が難しいレベルです。金管楽器は大音量が出やすいのでリスクはあります。それから85デシベル以上の音で、3デシベルという音圧の大きさが上がるにつれ、1日の許容時間が2分の1になるのです。85デシベルで、許容時間は1日8時間。3dBルールでいくと、110デシベル(コンサートやイヤホンで大音量を聞くとき)くらいだと許容時間が1〜2分となってしまいます。それを数年続けていると、耳に障害が出る可能性があります。耳栓のフィッティングの問題もあります。耳にぴったりし過ぎると、耳をふさいでしまいます。耳をふさいでしゃべってみてください。すごく響くでしょ。それと同じことが起こるのです。自分の楽器の音が身体を通して伝わりますので、それが妙な響きになります。その場合、作ってもらった人に相談し、自分が納得いくような音に調節してもらうのがよいですね。
クラシック音楽の場合、1曲のなかでの音の強弱の差が激しいです。f(フォルテ、強音)のあとに、いきなりpp(ピアニッシモ、弱音)を吹かなければいけない場合もあり、そこが大変です。
聴覚に携わっている者から見れば、聴覚保護の耳栓はしたほうがよいと思います。音響外傷の問題点は、音の大きさと聴く時間の長さです。
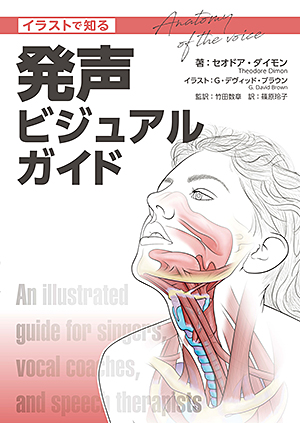
イラストで知る発声ビジュアルガイド
セオドア・ダイモン 著
竹田数章 監訳
篠原玲子 訳
【定価】2750円(本体2500円)
プロフィール

長 哲也(ちょう てつや)
東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。フランス国立リヨン高等音楽院大学院修了。第30回日本管打楽器コンクールファゴット部門第2位。同声会賞受賞。第48回北九州市民文化奨励賞受賞。2019年度文化庁新進芸術家海外研修生として、フランス国立リヨン高等音楽院大学院で学ぶ。2015年東京オペラシティリサイタルシリーズ「B→C」に出演。2018年フォンテックよりデビューCD『SOLILOQUY』をリリースし、『レコード芸術』にて特選盤に選ばれる。ソリストとして新日本フィルハーモニー交響楽団と共演。現在、東京都交響楽団首席ファゴット奏者。木管六重奏団「THE SIXTH SENSE」メンバー。東京音楽大学非常勤講師。

竹田数章(たけだ かずあき)
1959年生まれ、京都府出身。仙川耳鼻咽喉科院長。日本医科大学大学院博士課程卒業。医学博士。現在仙川耳鼻咽喉科院長。桐朋学園・洗足学園非常勤講師。音声生理学や臨床音声学の講義を行う。文化庁能楽養成会(森田流笛方)研修終了。趣味は音楽、スポーツ、観劇、フルート、書道。監訳書に『ヴォイス・ケア・ブック声を使うすべての人のために』(ガーフィールド・デイヴィス&アンソニー・ヤーン著、音楽之友社刊)、『発声ビジュアルガイド』(セオドア・ダイモン著、音楽之友社刊)。









